| 上荷船が発着した笠置浜 |

|
|
▲ 切山地区から見た笠置浜と笠置大橋
|
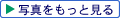 |
〔木津川水運の歴史〕
木津川は三重県の布引山地に発し伊賀盆地を流れ、南山城村の山間部で名張川と合して西流し、山城盆地に至って北上し宇治川、桂川との三川合流点で淀川となって大阪湾に流下する淀川水系の一級河川です。
木津川は、古くから近江・山城・大和地域だけでなく、淀川経由で国内各地や東アジア諸国を結ぶ水上交通路として重視されました。木津川市木津宮ノ裏の上津(こうづ)遺跡は、平城京の外港であった泉津(いずみのつ)の遺構と考えられています。
〔近世淀川水系の水運〕
淀川水系には、中世まで石清水八幡宮の支配下にあって淀を根拠地とする積載量20石の淀船(よどぶね)が、独占的体制を維持して運航していました。豊臣秀吉は、20〜200石積載の過書船(かしょぶね)に運上を課して淀川での営業独占権を与える制度をつくりました。過書というのは、海や河川の通航の関料免除を認めた手形のことです。過書船の制度は徳川家康に承継され、淀船を含めて過書座に組み込まれ、幕府の過書奉行の支配下となりました。
〔木津川の水運〕
木津川水運は淀船の独占でしたが、江戸時代になると、一口(いもあらい)、吐師(はぜ)、木津、加茂、瓶原(みかのはら)、笠置の浜では、10〜15石積載の上荷船(うわにぶね)と呼ばれる帆かけ船で浜の荷物を運ぶようになり、これら6か村は、木津川六か浜と呼ばれました。幕府は「六ケ所上荷船持」として管理・統制しました。運搬量は、淀船87%、上荷船13%と定められたようです。
上荷船への積荷は六ケ浜に限られ、御所宛の米や例幣使下行米、木柴などを載せ、淀・伏見だけでなく、木津川沿岸の祝園、平尾、玉水、高(多賀)、市野辺、天神森などや、宇治川の宇治、小倉、六地蔵、橋本へも通っていたようです(山城郷土資料館報第9号・田中淳一郎「江戸時代前期の木津川水運」による)。

|
|
▲ 木津川左岸から見た右岸の笠置浜
|
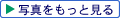
|
〔交通の要衝であった笠置浜〕
江戸時代の淀船、上荷船の遡上できる最上流の浜は笠置浜でした。木津川を遡上した船荷はここで降ろされ、馬持、馬借と呼ばれる陸上運送業者によって柳生方面やさらに上流の伊賀上野方面へと運ばれました。
笠置浜は、現在の笠置大橋付近に位置し、16世紀末に右岸の北笠置村に森島家が移り住み、大坂夏の陣の際に兵糧輸送に功があったとして御船役に指名され、その後、代々笠置船手支配を勤めました。文政12年(1829年)の北笠置村の名寄帳によれば、高持80軒のうち、1石未満の家が8割以上で、田畑を所有しない者も19軒ありました。これらの人々は、水上・陸上の運送に従事していたと思われます。また、対岸の南笠置村にも16世紀末に大和の十一氏の家来であった大倉家が移住し、代々庄屋を勤めました(同館報第7号・田中淳一郎「笠置町笠置森島家文書と笠置浜」による)。
〔水運権益を守ってたたかった笠置浜の人々〕

|
|
▲ 木津川右岸から見た左岸の笠置浜
|
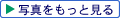
|
19世紀初めに笠置浜から藤堂藩・伊賀上野城下の小田浜までの高瀬船が再興されたとき、笠置浜は役人立会のもとで高瀬船方と交渉し、文化7年(1810年)、高瀬船の通船で笠置の茶屋・旅籠屋・店売などの「往還稼」が衰微する補償として、高瀬船方が笠置村に年銀1貫500匁を支払うとの和解を成立させています。
同じころ、上荷船減船の争論があり、淀船側が勝訴し、文化9年(1812年)の船改で木津浜では10艘の減船がありましたが、藤堂藩の領地の笠置浜は藩の御用を勤めを主張し、17株51艘の保有を維持しました。
天保3年(1832年)には、童仙房を除く上流の現南山城村の地域を領有する柳生藩が大河原村の浜から淀・伏見に通じる二十石船10艘の運航を企図した際には、御手船の運航で笠置浜が難渋し、亡所となるとして木津川六ケ村の惣代が過書奉行に差止の申立をしました(同・田中淳一郎「笠置町笠置森島家文書と笠置浜」による)。
このように、木津川六ケ浜、特に最上流の笠置浜の人々は、交渉や訴訟などを通じて木津川水運の権益を擁護し、住民の生活と地域の存続を守ってきたのです。
〔現代社会における権利の実現〕
現代の法治国家日本でも、権利の確保・実現は、交渉や訴訟、審査請求などの法定の手続きによるのが原則です。日本国憲法は、裁判を受ける権利(第32条)や裁判の公開(第82条)など裁判に関する規定を置いており、これにもとづいて民事訴訟法、家事事件手続法など多くの手続法が定められています。
現在、裁判手続きのIT化が進められています。裁判の迅速化や訴訟当事者の負担の軽減化が必要であることはいうまでもありませんが、IT化によって、訴えの提起の困難化や拙速な審理など裁判を受ける権利や裁判公開の形骸化があってはなりません。
|
| 2023年10月 |
|